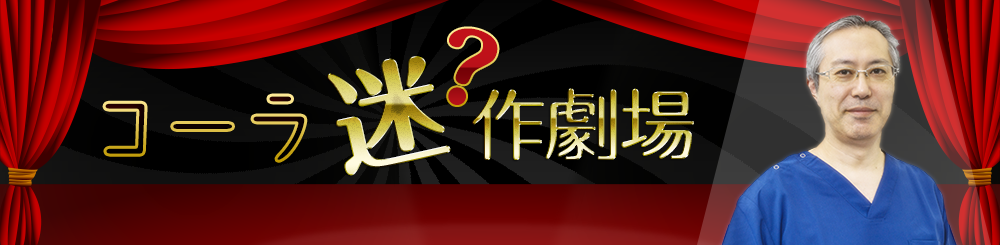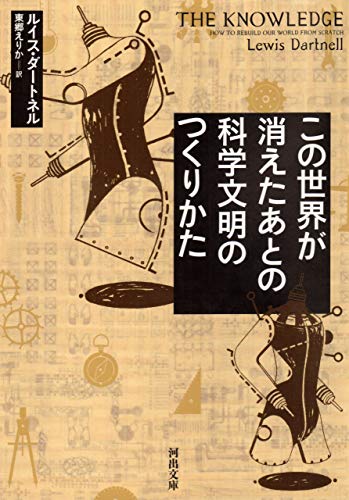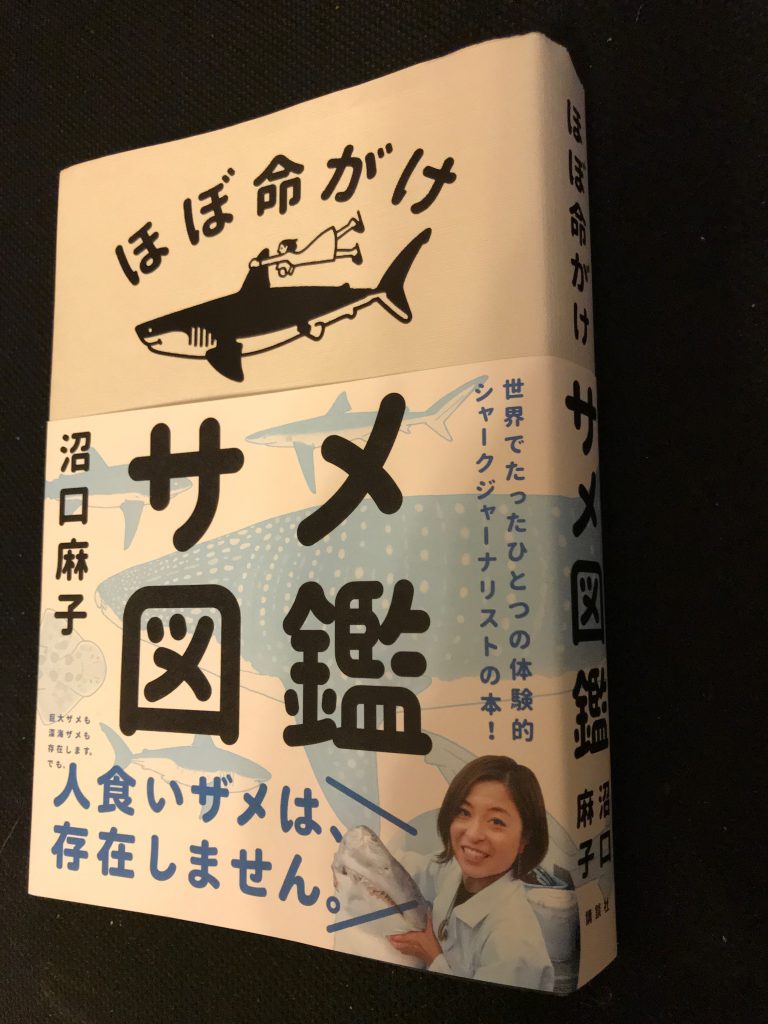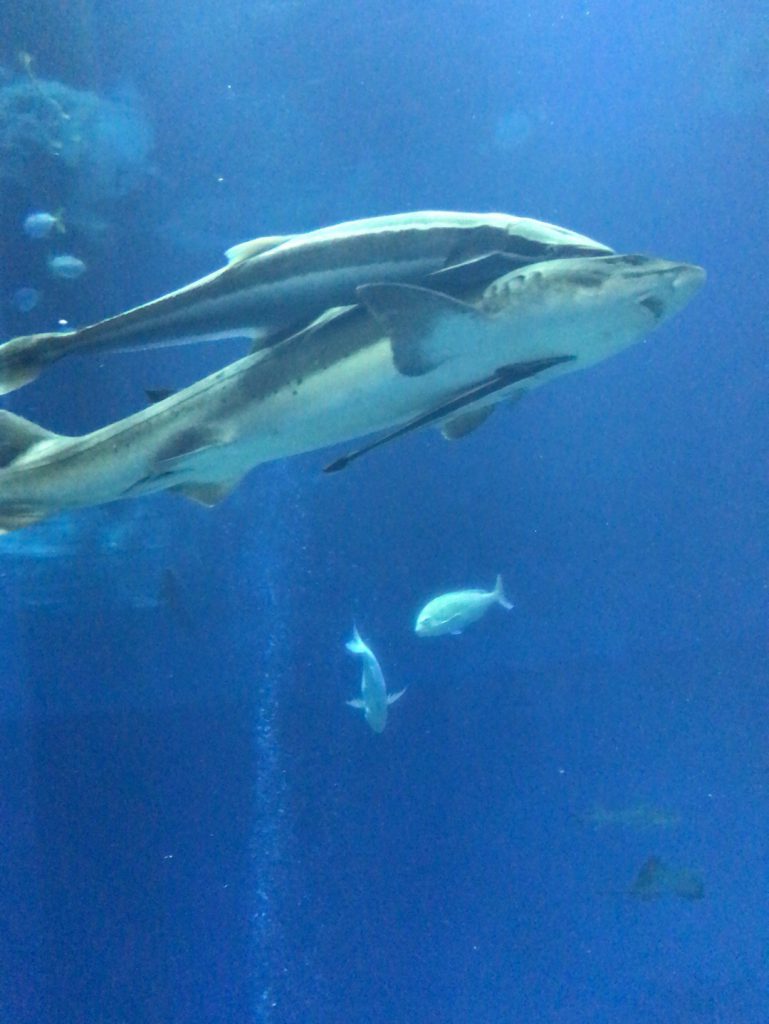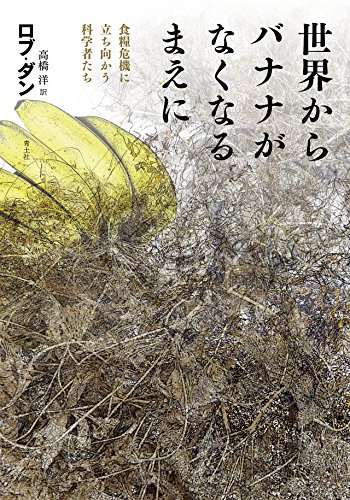 生物学的多様性、最近は「生物多様性」と言うんだった、その保全が農業の、いや、人類の未来を支えるのに必須であることを、進化生物学者の著者が、歴史上の事例の紹介を交えて解き明かす。
生物学的多様性、最近は「生物多様性」と言うんだった、その保全が農業の、いや、人類の未来を支えるのに必須であることを、進化生物学者の著者が、歴史上の事例の紹介を交えて解き明かす。
本書の邦題となっている、バナナの逸話が最初に語られる。かつては流通するバナナのほとんどを占めていたグロスミッチェルという品種は種子を結ばず、地下茎から生えだす吸枝を使ったクローン形態での繁殖を行うしかない。世界中の輸出用バナナが遺伝的に同一だったのだ。1890年にパナマ病の流行が起こった時、すべての農園が壊滅した。グロスミッチェルに似ていて、パナマ病に対する病害抵抗性を持つバナナはキャベンディッシュ種しかなく、キャベンディッシュに全部入れ替わった結果が我々の知るバナナの市場だ。キャベンディッシュも遺伝的に同一である。新パナマ病の脅威が近い。新たな技術と伝統品種の遺伝子を生かして、病害抵抗性を持つ品種を作り出さなければならない。
1845年から1849年のアイルランドのジャガイモ飢饉は、食物のジャガイモへの依存度が世界一高かったこと、ランパーというたった1つの品種が大規模に栽培されていたことなどから、ジャガイモ疾病のパンデミックにより起こった。当時のアイルランドの人口800万人のうち、100万人以上が死亡したのだ。
この話を読むと、ハンバーガー屋でフレンチフライを残すことができなくなる。カンボジア、ポル・ポト政権下の大虐殺で、人口750万人中、100万人以上が死亡したとされるが、同規模の悲惨な事態だったとイメージできる。
科学者たちが常に無力だったわけではない。アフリカでの重要なカロリー源、キャッサバがコナカイガラムシに脅かされたとき、害虫の天敵となるハチを利用して阻止することができた。
衝撃的なのは、1989年にブラジルのカカオプランテーションで発生した、天狗巣病の流行だ。一国の産業が崩壊した。感染した枝をロープで結わえ付けるという、単純な手法による農業テロだったことが後に判明する。犯行はたった6人の手により成し遂げられた。
天狗巣病はサクラにもある。そして、ソメイヨシノはすべて遺伝的に同一のクローンだ。病気の流行に対し非常に脆弱である。しかし、今年の花見の際にじっくりと観察したが、異常な枝は1本もなかった。一般人の知らないところで木々の管理が徹底されていることに、感謝の念を捧げよう。
病害抵抗性を持つ品種を見つけ出すために、野生種を含む世界中のすべての品種を集めた種子バンクの重要性が強調される。同様に、病害生物に対し天敵となる生物を探すためにも、すべての生態系が保護され、その情報がネットワークを通して利用できるようにするしかない。