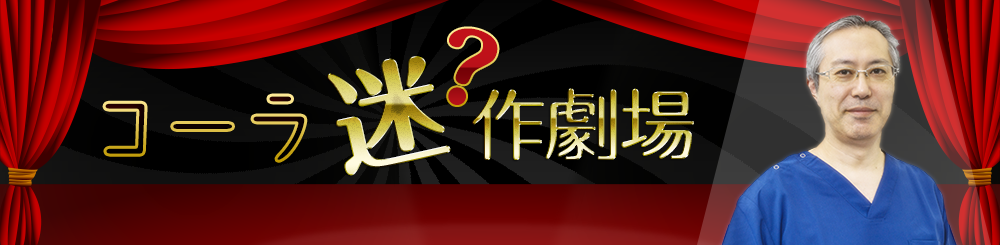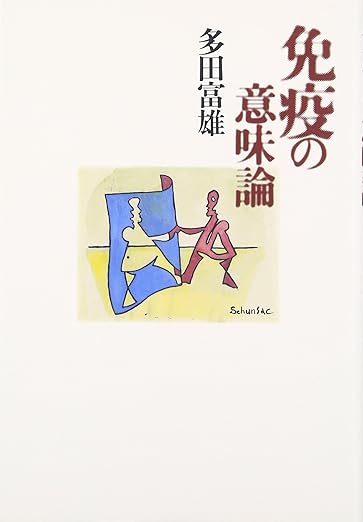今年のノーベル生理学・医学賞を阪口志文が「制御性T細胞」で受賞されましたが、東大時代の恩師多田富雄の提唱した「サプレッサーT細胞」とどう違ったのかをまとめてみました。
どちらも免疫反応を抑制するT細胞の概念ですが、成立した時代背景、証拠の有無、研究の進展によって大きく性格が異なります。
多田富雄の「サプレッサーT細胞」
1970年代の概念:多田富雄が提唱したのは1971年。ちなみに千葉大学教授から東大教授になったのは1977年でした(筆者はM1の学生)。
問題点:サプレッサーT細胞を明確に同定できる分子マーカーがなく、再現性の乏しい結果も多かったため、1980年代には幻の細胞とみなされ免疫学の主流から退けられました。
阪口志文の「制御性T細胞(Treg)」
1995年の発見:胸腺で分化するCD4+CD25+T細胞が自己免疫を防ぐ抑制的な役割を持つことを報告しました。のちに転写因子FoxP3がその分化と機能のマスター遺伝子であることを示し、Tregは免疫抑制の実在の細胞として国際的に確立されました。
特徴:1)分子マーカーで同定可能。2)自己免疫疾患や移植、アレルギーなどにおいて抑制機能を果たすことが実験的にも臨床的にも証明されました。3)免疫の負の制御が実体を持つことを明確にしました。
🔬🔬🔬🔬🔬
一度は否定された「サプレッサーT細胞」の概念ですが、歴史的な位置付けを考えてみると、免疫には抑制系があるという発想の出発点となっています。多田富雄はその挫折を正直に認めつつ、免疫の抑制系存在の直感は正しかったと後に語っています。阪口志文のTreg発見を喜び、自らの仮説が未来の発見の伏線となったことを誇りに思っていたということです。
1977年当時の東京大学医学部は「東大卒でなければ教授になれない」という慣習が強く残っていました。多田富雄が千葉大出身で東大教授になったのは慣習を打ち破る人事であり、免疫学という新しい学問の旗手として期待を集めたできごとでした。また、学生と一緒に新宿の裏通で飲むといった開かれた性格の方でした。